 昭和28年ごろ田村氏からの寄贈の最初の建物
昭和28年ごろ田村氏からの寄贈の最初の建物 昭和34年完成直後の作業棟
昭和34年完成直後の作業棟
障害者の楽園づくりに生涯を
創設者 田中皎一氏著書
いつのまにか耳が

創設者の田中皎一氏と藤川マキヱ氏
空知川の流れに沿い、なだらかに続く高さ100メートルたらずの山里の砂川市富平が、私の生まれ故郷である。あたり一帯は水田で、父母も四町歩余りの水田を所有していた。私は七人兄弟の末っ子で、小学校に入学してから四年生まで育った。それは私にとって忘れられない喜びと希望にあふれた毎日であった。
当時の学科に珠算があり、これも私の得意の一つであった。ところが、五年生の初めころより、見取算のときは満点なのに、先生の読み上げの時はどうしてか間違いが多く、その上、名を指されてもわからないときが度々あった。家庭では名前を呼ばれても返事をしないので、わかっていて返事をしないとか、ぼんやりしているとか兄達にいわれ、不思議に思ったものである。
私の耳は、急に聞こえなくなったのでなく、徐々に聴力が低下したもので、特別の痛みもなかったので、家の者は田畑の仕事に追われあまり気にもとめなかったように思う。六年生からは教室で最前列の席を与えられた。先生の問いに見当はずれの答えをして友達に笑われ、恥ずかしいやらくやしいやらで、泣きながら廊下にとび出したこともあった。それまで首位であった学業も落ち、それから甘えられぬ苦痛で、家庭に帰ってから参考書で夢中に学習したものである。
耳をなでてくれた母の感触
そんなとき、ふりむくと母がたっていて「出来ることなら、お前にわたしの耳をやりたいがなあ。」と心配そうに耳をなでて下さった感触が今も思い出されてならない。一家団らんのひとときもお話がきこえないので、私には何の楽しみもなくなった。床についても「兄や姉たちはみな健康で、希望ある毎日を過ごしているのに、私のみどうして聞こえないのか。いつになったら聞こえるようになるのか、いや、私は一生の間耳が聞こえない身ですごさねばならないのだろうか。」と悲しく思いつづけ、隣でやすんでいる母に気づかれまいと、声をころして枕をぬらしたものである。
思いをかためてろうあ学校に
その後青年学校に進んだが「何とかして他の人との対話が出来るようになりたい。」これが私の考えていた願いであった。私の習った小学校の国語教科書の中に、唖の子供に父母が面会に来た時「おとうさん」と呼び、また、父母の問いに答える感動的な対話がのっていた。私はこれにヒントを得て、私も唖の学校に入り、話しことばを、口を見てわかるようになりたいと考え、札幌のろうあ学校を尋ねたのである。
学校の玄関に入るやまず、青白い顔をして、私の方を物珍しげにきょろきょろ見つめる七、八歳のろう児が目についた。一瞬、何か見てはならないものを見た時のような、いやな気がした。ここで近藤校長先生におあいし「読話(相手の口を見て話を理解すること)を習得することは、そんなに短期間に出来るものではないので、ろう児に接しながらやってみてはどうか。また、職員として採用することも考えよう。」とのおことばを頂いたが、玄関で見たろう児の顔か頭から離れず、暗い気持ちで帰宅した。思えば同じ人間としてこの世に生まれながら、あの子たちは、私よりもっと聞こえず、生まれてより小鳥のさえずりも、やさしい父母のことばも聞いていないのだと思うと、自分もまた、あのろう児たちと同じろうあ者になったことを思いつめたとはいえ、さげすんで見ていた自分が何か恥ずかしく感じた。何とかしてこの人達の力になってあげようと意を決したのは、それから間もなくのことであった。
戦争をへてろう教員となる
昭和十八年四月十三日、この日は、私が札幌ろう唖学校の寄宿舎に入学し、教員助手とはいえ、児童と共に寝起きし、朝夕の世話から始まり、そうあ者のためにこの道への第一歩を踏みだす記念すべき日となった。努力のかいあって読話も予想以上に早く上達し、六か月後の九月、正式の教員として採用された。
当時しのぎをけずった日米戦争も、いよいよ急な折、私も二十一歳を迎え、徴兵検査を受けることになった。どうせ聞こえない身であり、今までに覚えた読話力で戦陣に立ち、一命を捧げんと決し検査場にのぞんだが、耳の聞こえない悲しさで、丁種合格になってしまった。検査官は「お前が国を思う心はよくわかるが、ろう者を教育する今の道に勤めることがまた一層国のためである。」と、こんこんと諭され、致し方なく引きさがったが、今もあの時のことばが思い出される。この時本当に自分が一人前でない人間であるということが強く感じられたのである。しかし、それだけに死んだと思って、一層この道に進もうと、日々のろう児の指導や世話に、精根の限りつとめたものであった。
本道にも敵機が襲来しはじめ、その危険をさけて、学校は十勝の御影に疎開、間もなく終戦となった。
昭和二十四年、晴れて文部大臣よりろう学校教員としての認可書の交付を受け、同じろう者の教育に没頭したのであるが、学校を卒業しても、何ら職業補導施設がないため、就職が困難で、やむなく家庭に帰さねばならぬ子の処置に胸を痛めるようになった。(現在のわかふじ寮の藤川理事長にお会いしたのはこの頃である。)何とかして卒業生の職業補導施設をと、方方あさり探したが、道内はもちろん、日本中のどこにも、ろうあ者の授産施設はなかった。その上、世の中が落ちつくにつれ、ろうあ者は、ろう学校の教員として不適当であるという声もきかれるようになった。
ろう者の授産施設の建設に
私はここで意を決して、八か年のろう教育より身を引き、まず御影家庭園に入った。昭和二十六年春であった。ここでは慣れない手にスコップ、ツルハシを持ち、木の根を掘り池をつくるなど、施設づくりから仕事を始めた。皆の協力でこの家庭園を財団法人から社会福祉法人へ組織を変更することにも成功し、やがて施設の運営も軌道にのってきたので、いよいよ、ろう者達の授産施設も本格的に考えるようになった。
私の教え子が一様に工作に興味をもち熱心であることに着目し、木工の授産施設を建設することに着目し、木工の授産施設を建設することに決心した。決まればいろいろと糸口も出来るもので、木工の場合、一番大切な木材資源の豊かな新得町で、木工場、建築請負、家具製作販売などと、幅広い事業を営んでおられた田村政雄氏の協力が得られることになり、宿望のこの大事業に着手したのである。
特別の財源は所有する由もないが、はじめ落ち着いた所は新得町東一線の製菓工場の住宅であった。もちろん田村氏の所有である。早くも私の教え子が二人集まってきた。
はじめは独立した施設は皆無なので、まず田村氏の従弟の方が経営している石川家具製作所に私はこの二人と入所した。日給二〇〇円の職工と同じである。田村氏も石川氏も大変度量のある立派な方であるが、耳の聞こえない者に接するのは初めてで、何かと誤解されることがあった。親切に何度も話して下さるのだが、下を向いての作業中は、何を言われてもわからないので知らない顔をして自分の好きなようにやっていると、とられることもあり、よく注意を受けた。一方、私たちも真面目に働いているのに、どうして小言を言われるのかわからず「不親切な主人だ」とこぼすこともあった。
耳の聞こえない人の実状を知らせる
このような中に立って私も聞こえない一人だが、憩いの時などを利用して、耳の聞こえない人は視線が向いていて、神経がそそがれていなければ、どんな大声で話して下さってもわからないということをお伝えした。また、ろう者にも、ここのご主人は、お金もうけの考えはなく私たちに技術を教えて下さろうと骨折っておられるのだと何度も話し、心から敬う気持ちをもってもらうよう努めたものであった。
間もなく、田村氏のお骨折りで、西一線の今のわかふじ寮のある所にあった木造七十坪程の建物に移った。中学校の前でもあり、環境のよい、施設にふさわしいもってこいの場所と感激し喜びあったものである。入所者も一人、二人と増加し、ろう者の楽園、授産施設の建設を目指して建築用の砂利運びに精出した。
またある時は、耳の聞こえない人たちの実状を社会に訴え、活路を開きたいものと、自分の話し声の高低もわからない身ながら、十勝地区社会福祉建設の青年弁論大会に出席し十勝支庁長や福祉関係者の前で、耳の聞こえない人の立場を論じたこともあった。
社会福祉法人として認可される
一方どんな充実した施設内容でも、社会福祉法人の組織でなければ、法的に認められないので寸暇をさいて、法人申請の準備を進めた。月々の稼働収入も寮生の食費にまわり、実家に仰いだ援助もこれ以上母を煩わすにしのびず自らの生活費をおさえて運動資金とし、法人としての財産整備に奔走した。条件すれすれの内容であり、幾度も役所をたずね指導を仰いだものである。
暮れもさしせまった昭和二十九年の十二月二十日に新得町社会福祉協議会から事情をみかねて資金の一部にと一万五千円が贈られた。法人の認可をと藤川先生と二人で、この贈られた資金に手持ちの五千円を合わせ、僅か二万円を懐に上京し、厚生省や国会へ日参し陳情を重ねたのもこの時である。
この陳情後、翌年の五月、厚生省から現地調査に見え、発足以来三年目の昭和三十年十二月二日付で、宿望の社会福祉法人として認可になったのであった。ここに晴れて共同募金なども配分いただけるようになり、指導室や、機械設備も着々と整い、田村氏にお世話になった経営からはっきり分離し、家具や建具の木工授産所として独立に遁進したのであった。法人として認可を受けるまでのそれは、ほんの一言でいえる三年間ではあったが、十年にも恩われる汗と涙の毎日であった。
将来の見通しが明るい(身体障害者の授産施設・第一号、5施設の中に入る)
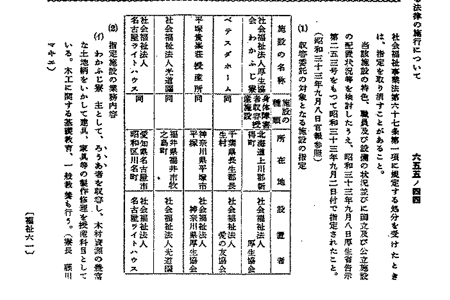 基礎が出来れば次の発展も早く昭和三十三年には身体障害者の授産施設として全国で初めてのケースで、厚生省の指定を受けることが出来た。三十五年には乾燥室と機械設備が増加され入所者は定員五十名を五名も越え、かつて施設づくりに一つ鍋をつついた教え子も、今は技術指導員として、自らが歩んだ体験を生かして後輩の指導に専念している。年毎に社会に送り出した修了者も五十余名となり、わかふじ寮での技術指導に生活指導の成果が実り、私以上に聞こえない人たちも就職先の先輩や同輩と円満に和合し、身につけた技術を生かして、いいあわせたように豊かな生活をしているのは嬉しいことである。私が今日の日を迎えたことは、もちろん私一人の力だとは思っていない。藤川先生が絶えず私を案じ指導して下さったお蔭であり、私の身近な職員の協力の賜であり、私を支えてくださる社会の方のお蔭に他ならない。私は、私の人生の終着駅に至るまで、もっと、もっと、わかふじ寮の充実のため努力していく決心でいる。私共の耳の聞こえないということは、かくしおおせるものではない。何かの折に悩み、何かの折に迷うこともあるだろうが、そんな時の灯として、わかふじに、いつまでも、いつまでも私たちの心の灯をともしておきたいと願っているのである。
基礎が出来れば次の発展も早く昭和三十三年には身体障害者の授産施設として全国で初めてのケースで、厚生省の指定を受けることが出来た。三十五年には乾燥室と機械設備が増加され入所者は定員五十名を五名も越え、かつて施設づくりに一つ鍋をつついた教え子も、今は技術指導員として、自らが歩んだ体験を生かして後輩の指導に専念している。年毎に社会に送り出した修了者も五十余名となり、わかふじ寮での技術指導に生活指導の成果が実り、私以上に聞こえない人たちも就職先の先輩や同輩と円満に和合し、身につけた技術を生かして、いいあわせたように豊かな生活をしているのは嬉しいことである。私が今日の日を迎えたことは、もちろん私一人の力だとは思っていない。藤川先生が絶えず私を案じ指導して下さったお蔭であり、私の身近な職員の協力の賜であり、私を支えてくださる社会の方のお蔭に他ならない。私は、私の人生の終着駅に至るまで、もっと、もっと、わかふじ寮の充実のため努力していく決心でいる。私共の耳の聞こえないということは、かくしおおせるものではない。何かの折に悩み、何かの折に迷うこともあるだろうが、そんな時の灯として、わかふじに、いつまでも、いつまでも私たちの心の灯をともしておきたいと願っているのである。
「はたらきたい~身心障害者の職業自立に-J北海道社会福祉協議会編
北書房版に昭和40年に掲載、当時、わかふじ寮指導主任を行っていた田中氏が執筆




























